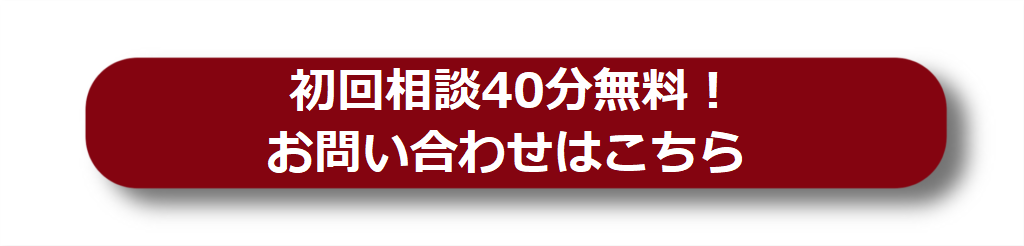本記事の内容
・ I. 事業再構築補助金の概要と目的
・ II. 事業再構築の定義と対象取組
・ III. 補助対象者と申請要件
・ IV. 類型別の補助金額・補助率・経費
・ V. 申請から交付までの流れ
・ VI. 注意点とリスク
・ VII. 採択を有利にする加点項目
・ VIII. 制度の終了と後継制度
・ IX. 第1回~13回の採択傾向分析
ポストコロナ時代に新たな事業転換を検討する中小企業経営者の皆様へ。
本記事では、行政書士が現場の申請支援経験に基づき、「事業再構築補助金」の制度全容、申請要件、採択を左右するポイント、そして後継制度までを網羅的に解説します。
I. はじめに:事業再構築補助金の概要と目的
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の長期化で需要が減少した企業に対し、「思い切った事業再構築」を支援する制度として2021年に創設されました。ポストコロナ時代の構造変化に適応し、日本経済全体の生産性を底上げすることを目的としています。
【実務メモ】
弊所でも2021年以降、多数の採択支援を行ってきました。コロナ渦ではコロナ対策を主とした事業が中心的に採択され、アフターコロナでは企業が生き残るための革新的な取り組みに採択の重きが置かれておりました。後継の新事業進出補助金も時代の流れを汲みとり、適切な投資を行うことが1番大切です。
こちらは2025年度の事業再構築の記事です。
II. 事業再構築の定義と対象取組
経済産業省が定める「事業再構築指針」に基づき、6つの類型が対象となります。
- 新市場進出(新分野展開・業態転換)
- 事業転換・業種転換
- 事業再編(合併・会社分割・事業譲渡等)
- 国内回帰
- 地域サプライチェーン維持・強靭化
III. 補助対象者と申請要件
A. 補助対象者
- 日本国内に本社を有する中小企業者・中堅企業等
- 法人税法別表第二該当法人(収益事業を行う場合)
- 社会医療法人(収益事業限定)
B. 申請要件
- 事業再構築指針に沿った3〜5年の事業計画策定(認定支援機関確認必須)
- 付加価値額の年平均成長率3〜5%以上を目標
- 一部類型を除き、売上15%以上減少の実績
IV. 類型別の補助金額・補助率・経費
A. 主な事業類型
- 成長分野進出枠(通常類型):最大6,000万円(賃上げ時最大7,000万円)/補助率1/2(条件付2/3)
- GX進出類型:最大8,000万円(賃上げ時1億円)/補助率同上
- コロナ回復加速化枠:最大1,500万円/補助率3/4
- 物価高騰対策・回復再生応援枠:最大1,500万円/補助率3/4
- 産業構造転換枠:廃業費含め最大+2,000万円上乗せ
B. 共通経費
建物費、機械装置費、技術導入費、専門家費、広告宣伝費、研修費等。
交付決定前の契約・発注は補助対象外(事前着手制度は廃止)。
V. 申請から交付までの流れ
- GビズIDプライムの取得(2〜3週間要)
- 認定支援機関と事業計画策定
- 電子申請(公募期間中に専用システム経由)
- 審査・採択通知→交付決定
- 実施→実績報告→確定検査→補助金支払い
- 完了後5年間の事業化報告義務
VI. 注意点とリスク
- 採択=交付確定ではない。交付審査での減額リスクに注意。
- 補助金は後払い。資金繰り計画を必ず立てる。
- 付加価値額目標未達の場合、返還リスクあり。
- 不正受給は刑事罰対象。虚偽申請・目的外使用は禁止。
- 一次産業・長期賃貸事業・重複案件は原則対象外。
【実務コメント】
採択後の交付申請で減額されるケースは非常に多いです。
特に「見積書不備」「交付決定前契約」「賃上げ証明漏れ」は典型的ミス。初回申請よりも“交付手続の正確性”が重要になります。
VII. 採択を有利にする加点項目
- ワークライフバランスや職場改善の取組
- 大幅な賃上げ(成長分野進出枠)・最低賃金引上げ(回復加速化枠)
- 認定支援機関・専門家の支援を受けた事業計画
- パートナーシップ構築宣言の実施
- EBPM(政策効果検証)への協力
- 債務借換・事業再生の実施
VIII. 制度の終了と後継制度
- 第13回公募(2025年3月26日締切)で受付終了。
- 「事前着手制度」も完全廃止。
- 後継制度として「中小企業新事業進出補助金」が新設予定。こちらの別記事で解説させて頂いております。
- 新市場開拓・高付加価値事業への設備投資支援に移行。
IX. 第1回~13回の採択傾向分析
1. 採択率の推移:応募件数・採択件数と採択率の変化
採択率(全体)は公募回によって大きく変動しました。第1回公募では応募約22,000件に対し採択8,016件で、採択率は約36%とやや低めのスタートでした。その後、第2~5回は40%台前半、第6~8回には50%前後まで上昇し、第8回では採択率51.3%とピークに達しました。これは応募件数の減少(第1回約22,000件から第8回約12,591件へ減少)に伴って相対的に採択されやすくなったことが一因です。例えば応募数が減少傾向にあった第6~8回では、応募の4~5割が採択されていました。
しかし、第9回以降は傾向が変わります。第9回・第10回は採択率45~48%程度とやや低下し、第11回では2割台後半(約26.5%)まで大幅に低下しました。具体的には、第11回公募では応募9,207件中2,437件採択で約26.5%に急落しています。この急低下の背景には、政府の厳格なチェックによる審査基準の引き締めがあります。実際、令和5年(2023年)秋の行政事業レビューで本事業への厳しい指摘があり、中小企業庁はそれを踏まえて審査を見直したとされています。また第12回からは口頭審査(プレゼンテーション等)が加わり、審査は一段と厳格化されました。こうした影響で第12回も採択率26.5%(応募7,664件に対し採択2,031件)と低水準が続きました。
最終となった第13回公募では応募件数が3,100件と大幅に減少した一方、採択数1,101件・採択率35.5%とやや改善しました。応募減少は後継の新制度が発表されたためと推測されますが、採択率上昇について事務局は「直前まで20%台では厳しすぎた」という声も上げています。いずれにせよ、全期間を通じた採択率の推移は「初期は3割台→中期は5割前後まで上昇→終盤で2割台に急落、一部回復」という曲線になりました。この変動は予算消化状況や政策方針の転換(審査基準の厳格化、応募内容の質向上要求など)によるものと分析できます。
2. 業種別傾向:申請・採択の多い業種と業種ごとの採択率
業種別の採択状況を見ると、製造業が終始目立ちます。例えば最新の第13回では、製造業が応募全体の22.9%を占める一方、採択者全体の33.8%を占めており、明らかに高い採択率を示しました。第11回でも製造業は応募約19.7%に対し採択約30.3%と突出しており、他業種より採択されやすいことが伺えます。「ものづくり」の具体的な設備投資を伴う計画は成果がイメージしやすく、国の産業政策の軸に合致しやすいため、審査上有利だったと言えるでしょう。
一方、卸売業・小売業や建設業も毎回一定の存在感があります。第13回では卸売・小売が応募14.9%・採択14.4%、建設業が応募13.4%・採択14.2%と、いずれも応募割合と採択割合がほぼ同程度で安定した結果を残しました。これら業種も設備投資型の事業計画が多く、比較的採択に結びつきやすかったと考えられます。
対照的に、サービス業種の一部は採択率が低めでした。例えば宿泊業・飲食サービス業について、第1回では製造業と並び応募・採択件数ともに最多クラスで、両業種合わせ応募全体の4割弱・採択全体の5割強を占め、採択率も高い好結果でした。これはコロナ禍で打撃を受けた飲食・観光業への支援意図が強かったためと考えられます。しかし回を追うごとにこの傾向は変化しました。第11回を見ると宿泊業・飲食サービス業は応募割合11.5%に対し採択割合8.4%と低調で、応募シェアの割に採択が少ない業種になっています。同様に生活関連サービス・娯楽業も応募7.0%に対し採択3.4%とかなり厳しい結果でした。これらは新規性や成長性の観点で計画内容が審査を通りにくかった可能性があります。つまり無形サービス中心の業種では、計画の根拠や実現性をしっかり示さないと採択は容易ではなかったと推察できます。実際、第13回でも情報通信業や専門サービス業など無形資産主体の業種からの採択事例は一定数ありましたが、「業種にかかわらず計画の精度と根拠がカギ」という評価でした。
総じて、製造業は終始有利であり、次いで卸売・小売、建設などリアルな事業資産を伴う業種が堅調でした。コロナ直後は宿泊・飲食も重点支援されましたが、後半では製造業など成長志向の業種がより高評価となる傾向が強まりました。これは補助金の趣旨が「危機からの立て直し」から「成長への投資」へ移行したことを反映しています。
3. 申請類型別の傾向:通常枠・特別枠・グリーン成長枠などの動向
事業再構築補助金では、公募回ごとにいくつかの申請類型(枠)が設定されました。主要なものとして「通常枠(第10回以降は成長枠に改称)」「緊急事態宣言特別枠」「グリーン成長枠」などがあり、それぞれ採択動向に特徴が見られました。
通常枠(成長枠):最も一般的な枠で、第1~9回は「通常枠」、第10回以降は要件変更に伴い「成長枠」と呼ばれました。初期の通常枠では売上減少(30%以上)要件がありましたが、第10回からは売上減少要件が撤廃され、市場規模10%以上成長分野進出や給与総額年平均2%以上増加など前向きな条件が加えられました。採択率は第1回約30%から上昇し、第6~8回は40%台後半、第11回では27.8%と大幅低下しています。応募件数も第1回約17,000件から第11回約2,500件へ減少しており、制度変更と支援ニーズの一巡が影響したと考えられます。
緊急事態宣言特別枠(特別枠):第1~3回頃に設けられ、コロナ禍で売上が大幅に減少した事業者を対象とした特別枠です。その採択率は非常に高く、第1回では通常枠30.1%に対し特別枠55.3%と倍近い差がありました。その後も第10回頃まで50~66%前後と高水準を維持しましたが、第11回以降は審査厳格化に伴い25.6%に急落しました。終盤では「特別だから通りやすい」という状況も解消され、他枠と同等の審査基準で評価されました。
グリーン成長枠:脱炭素やエネルギー転換を目的に第6回(2022年)から新設。環境関連の大型投資案件が多く、初期は採択率40%前後とやや低めでしたが、第11回では31.3%と他枠よりやや高水準を維持しました。これは国のグリーン政策を反映した優遇傾向であり、環境分野は終盤にかけて加点評価されやすい枠でした。
また、「卒業枠」(中堅企業への成長促進)や「最低賃金枠」(賃上げ影響企業支援)も限定的ながら存在しました。特に最低賃金枠は第8回で採択率約70%と高水準を記録しており、条件適合企業には有効な選択肢でした。
4. 地域差:都道府県別・地域ブロック別の申請・採択傾向
地域別に見ると、第1回では「東高西低」の傾向が見られ、東日本の採択率が相対的に高く、西日本では低い結果となりました。東京都は応募最多ながら競争激化により採択率は平均以下でした。第12回時点では、全国平均26.5%に対し、高知40.0%、石川39.8%、岩手37.5%、群馬37.0%、福井35.2%と地方県の健闘が目立ちました。これらは「製造業比率の高さ」「認定支援機関による支援体制の充実」などが要因と分析されています。
一方、沖縄14.4%、北海道16.9%、鹿児島19.7%、山口20.8%、愛媛21.7%などは平均を下回りました。これら地域では申請支援体制の不足や応募件数の少なさが課題とされます。都市部では東京20.5%、大阪26.8%、愛知33.5%と差があり、産業構造・支援環境の違いが反映されています。総じて「地方だから不利・都市だから有利」ではなく、各県の支援体制と事業計画の質が採択率を左右したと考えられます。
第1回~第13回の総括:制度の変遷と今後の留意点
創設初期(第1~2回)は新型コロナの経済打撃からの救済目的が強く、高採択率かつ特別枠中心の支援制度でした。中盤(第3~9回)はポストコロナの成長支援型に転換し、成長枠・グリーン枠・最低賃金枠が導入されました。第8回では採択率50%超とピークに達し、質と量が両立する時期でした。終盤(第10~13回)は審査厳格化・プレゼン導入などにより採択率が急落し、選別色が強まりました。最終的に全13回で約20万件超応募・5万件超採択となり、多様な業種が新事業に挑戦しました。
本制度の教訓として、①新規性・成長性と実現可能性の両立、②政策方針(脱炭素・DX・賃上げ等)との整合、③専門家との連携が成功の鍵であると整理できます。特に「市場規模や顧客根拠の明確さ」「定量的な裏付け」「国策テーマとの親和性」が評価される傾向にあります。後継の「中小企業新事業進出補助金」でもこの流れを踏襲すると見られ、今後もデータに基づく実現性ある計画立案が最重要となるでしょう。
関連記事はこちら
| 事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
|---|---|
| 英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
| 代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
| 所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
| 取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
| TEL | 075-241-3150 |
| 営業時間 | 9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】 ※メールでの相談は年中無休で受付けております。 |