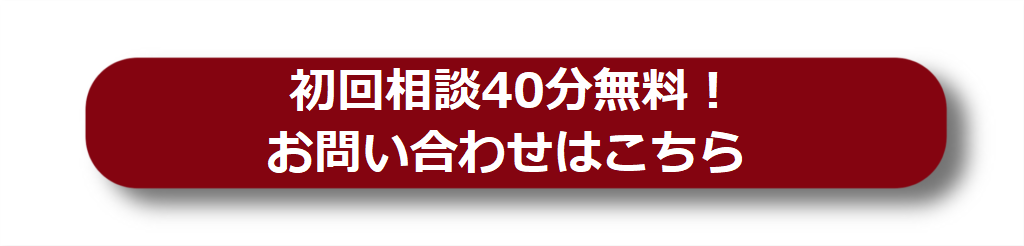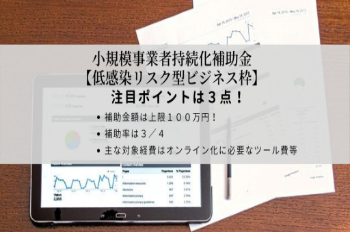本記事の内容
・ I. はじめに:ものづくり補助金の現状と採択傾向
・ II. ものづくり補助金の基本的な理解
・ III. 採択率の推移とその背景
・ IV. 採択される事業計画の評価ポイント
・ V. 多岐にわたる採択事例
・ VI. 申請を成功させるための実践的ポイント
・ VII. 2025年の主な変更点
・ VIII. 成果事例の探し方と情報源
・ IX. まとめ
I. はじめに:ものづくり補助金の現状と採択傾向
A. ものづくり補助金の概要と目的
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が、革新的な新製品・サービスの開発、試作品の作成、または生産プロセスの改善などを目的とした設備投資を支援する国の補助金制度です。これにより、企業の競争力強化と生産性向上を促進することを目的としています。2013年の開始以来、中小企業の成長を後押しする重要な施策として活用されてきました。
B. 近年の採択状況と審査の厳格化
しかし、近年ではものづくり補助金の採択を取り巻く環境は厳しさを増しています。かつては50~60%台の高い採択率を記録した時期もありましたが、近年はその傾向が大きく変化し、30%台前後で推移しています。直近の公募回では、第18次公募で35.8%、第19次公募では31.8%と、さらに採択率が減少しており、採択のハードルは年々高まる傾向にあります。これは、審査の厳格化と予算枠の減少が複合的に影響しているものと考えられます。
II. ものづくり補助金の基本的な理解
A. 制度の対象と支援範囲
ものづくり補助金は、革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善などに取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度です。その対象は製造業に限定されず、小売業、卸売業、サービス業など、すべての業種の事業者が利用可能です。補助の対象となる主な経費としては、機械装置、システム構築、技術導入、原材料費などが挙げられます。
B. 国の政策目的との連携
ものづくり補助金は、単なる設備投資の支援に留まらず、国の政策目的との連携も重視されています。具体的には、地域経済への貢献、賃上げ、デジタル化、脱炭素、海外市場開拓といった政策課題に合致する事業が奨励されます。これらの特定の政策目的に対応するため、「特別枠」も設けられており、申請事業が国の目指す方向性と合致しているかどうかも重要な評価項目となります。
III. 採択率の推移とその背景
A. 過去の採択率の変動と傾向
ものづくり補助金の採択率は、公募回によって大きく変動してきました。過去には第8次から第13次公募にかけて60%前後と高採択率を維持していましたが、第14次以降は50%前後に低下し、直近では30%台まで減少しています。このように、採択率は時代や状況に応じて変化する傾向にあります。
B. 採択率を左右する主な要因
- 審査の厳格化と予算枠の減少: 審査基準が年々厳しくなり、また予算枠が減少傾向にあることが採択率低下の大きな要因です。
- 申請件数の多寡: 申請件数が多い公募回では、相対的に採択率が低下する傾向があります。例えば、第4次締切では申請件数10,312件に対して採択率30.8%、第1次締切では申請件数2,287件で採択率62.5%でした。
- 特殊な公募背景:
- 第10次公募:新型コロナウイルス感染症の影響による救済的措置により、60%以上の高採択率。
- 第17次公募:「省力化(オーダーメイド)枠」のみの募集で申請数629件と少なく、採択率に影響。
IV. 採択される事業計画の評価ポイント
採択を勝ち取るためには、審査項目を踏まえた質の高い事業計画の作成が重要です。
A. 革新的な取り組み
自社にとっての新製品・新サービス開発、地域・業界における新技術導入など「革新性」を明確に打ち出す必要があります。単なる設備更新ではなく、未来志向の挑戦が求められます。
B. 具体的な生産性向上効果
生産性向上の効果を定量的に示すことが必須です。作業負担削減率や効率向上率など、数値的根拠を提示しましょう。QCD(品質・コスト・納期)の改善、新付加価値の創出も重視されます。
C. 事業計画の具体性
審査項目に沿い、取組内容・将来展望・付加価値額算出根拠などを明確に記載します。市場性や収益性もデータに基づき説明する必要があります。
D. 技術面・事業化面・政策面での整合性
- 技術面: 技術革新性と課題解決の明確化。
- 事業化面: 市場性、収益性、生産性向上、投資回収可能性。
- 政策面: 地域経済・賃上げ・デジタル化・脱炭素・海外展開など国の方針との一致。
E. 加点項目の活用
経営革新計画認定、賃上げ表明、DX認定、健康経営優良法人などの加点項目を意識的に盛り込むことで採択率が向上します。個人事業主も対象となる加点を検討しましょう。
F. 適切な申請時期
締切直前は申請集中で不備リスクが高まります。早めの準備と提出が有利です。
V. 多岐にわたる採択事例
A. 製造業の事例
- 自動車部品製造:ゴム製造技術を応用し、一般医療機器を開発。
- CFRP成形メーカー:炭素繊維素材で二足歩行アシスト装具を開発。
- プラスチック成形業:高品質化・生産能力向上のための機械導入。
- 製菓・食品機械メーカー:バウムクーヘンオーブン開発により海外展開。
- 金属リサイクル企業:破砕機改良でリサイクル率75%、銅純度87%を達成。
- 金属部品メーカー:提案型ビジネスモデル転換による自社製品開発。
B. 印刷業の事例
- 4色印刷機導入による受注拡大・顧客獲得。
- 検査機導入による自動化・業務軽減・信頼度向上。
C. 農業分野の事例
- 紫蘇加工企業(熊本):ICT圃場管理と自動選別システム導入。
- 柚子加工企業(G社):柚子ピール新商品開発と設備導入。
D. サービス業・飲食業・小売業の事例
- 家具店:顧客体験強化のためのVRシステム導入。
- 結婚式場(鳥取):インバウンド向け「ブライダルツーリズム」開発。
- 食品製造工場:AIによる不良品検出システム導入。
E. その他の成果事例
陶器メーカーが欧米向け高級陶器生産設備を導入し、国際競争力を強化。
VI. 申請を成功させるための実践的ポイント
ものづくり補助金の採択を勝ち取るためには、戦略的な準備と実行が不可欠です。
A. 公募要領の徹底理解と事業計画書の作成
公募要領を隅々まで理解し、自社の強みや課題を正確に分析した上で、質の高い具体的な事業計画書を作成することが最も重要です。審査項目である「革新性」「生産性向上効果」「事業の具体性」「技術面・事業化面・政策面での整合性」を明確に示す必要があります。
B. 申請時期の考慮と余裕を持った準備
締切日直前の駆け込み申請は、電子申請システムの混雑や準備不足による不備のリスクを高めます。余裕を持って申請準備を進め、計画的な提出を心がけましょう。
C. 専門家によるサポートの活用
ものづくり補助金の申請は複雑なため、専門家のサポートが有効です。金融機関、民間コンサルティング企業、行政書士、税理士、商工会・商工会議所などが支援実績を持っています。特に認定支援機関に登録されている専門コンサルタントは、多数の採択実績があり、採択率を高めるためのノウハウを提供しています。
D. 採択後の手続きと遵守事項
採択された後も、交付申請、補助事業の実施、実績報告、確定検査・金額確定、補助金の請求と支払い、そして事業化状況の報告など、一連の手続と期限を厳守する必要があります。これらの段階を円滑に進めるためにも、計画的な管理が求められます。
VII. 2025年の主な変更点
ものづくり補助金は年度ごとに制度が見直され、2025年には以下の変更点が予定されています。
A. 補助上限額の変更
- 従業員数に応じた区分制を導入。
- グローバル枠:最大3,000万円。
- 従業員51名以上の企業:上限2,500万円。
B. 新たな要件の追加
- 給与総支給額の年平均成長率の達成義務。
- 「一般事業主行動計画」の公表義務。
C. 収益納付制度の廃止
過去に存在した「収益納付制度」は廃止され、事業化後の収益に対する納付義務はなくなりました。
VIII. 成果事例の探し方と情報源
過去の採択事例を調べることは、採択の傾向を理解するうえで非常に有効です。
A. ものづくり補助事業公式ホームページ
「ものづくり補助金総合サイト」では、「もの補助成果事例検索」機能が公開されています。平成24年度補正から令和元年度事業までの6,000件超の事例を閲覧可能です。
B. 経済産業省 中小企業庁「ミラサポPlus」
「ミラサポPlus」では、過去の補助金活用事例が紹介されています。製造業での高精度マシニングセンタ導入、小売業でのVR体験導入、陶器メーカーの欧米向け生産設備などが掲載されています。
C. 各都道府県中小企業団体中央会
各地の中小企業団体中央会が発行する「ものづくり補助金成果事例集」では、地域密着型の成功事例を確認できます。山形県・宮崎県など、多くの中央会がウェブ上で公開しています。
IX. まとめ
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の革新と生産性向上を支援する国の主要施策です。しかし、審査は年々厳格化しており、採択率は30%台に低下しています。
採択の鍵は、革新性と生産性向上を具体的な数値と根拠で示すこと。技術面・事業化面・政策面の整合性を意識し、加点項目を活用しながら余裕を持って申請することが成功への道です。
また、2025年度からの要件変更(補助上限・給与総額要件・行動計画公表義務など)にも注意し、常に最新の公募要領を確認しながら計画的な申請を行いましょう。
関連記事はこちら
| 事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
|---|---|
| 英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
| 代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
| 所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
| 取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
| TEL | 075-241-3150 |
| 営業時間 | 9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】 ※メールでの相談は年中無休で受付けております。 |