
2025年度中小企業省力化投資補助事業(一般型)について解説致します。
本記事の内容
・ 【令和7年度】「中小企業省力化投資補助金(一般型)とは?人手不足解消と生産性向上のための国の支援策を徹底解説」
・ 「補助対象となるのはどんな事業者?申請前に確認すべき基本要件と対象外となるケースを詳しく解説」
・ 「いくら補助される?補助上限額と補助率、大幅賃上げ特例を活用するための条件と注意点」
・ 「中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請方法と審査のポイント:電子申請の流れ、事業計画書の書き方、加点項目」
・ 過去の採択事例から学ぶ傾向について
・ まとめ
【令和7年度】「中小企業省力化投資補助金(一般型)とは?人手不足解消と生産性向上のための国の支援策を徹底解説」
中小企業省力化投資補助金(一般型)は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しし、 人手不足に悩む中小企業等が省力化投資を実施することで付加価値額や生産性を向上させ、 併せて賃上げにつなげることを目的とした支援制度です。
- 事業の目的: 国内における人手不足の深刻化に対応するため、IoT・ロボット等のデジタル技術を活用した「省力化投資」への 補助を行うことで、中小企業の成長と賃上げを支援します。
- 対象となる省力化投資: AIやIoT、ロボットなどを用いた専用設備の導入、既存工程の自動化・効率化、DX化による 労働集約度の大幅削減などが想定されています。
- 一般型とカタログ型の違い: カタログ型は事前に登録された標準設備を導入するため手続きが簡易ですが、 一般型は導入設備のカスタマイズや独自要素が多く、審査項目が増える傾向にあります。
- 人手不足解消への貢献: 専用設備やロボット導入により、生産工程を自動化・省人化し、従業員の労働負担を軽減しつつ、 生産性向上を図る取り組みが期待されます。
A. 中小企業省力化投資補助事業(一般型)は、人手不足に悩む中小企業や小規模事業者の売上拡大、生産性向上を後押しするために、IoT・ロボットなどの人手不足解消に効果がある設備を導入する際の費用の一部を補助し、省力化投資を促進することを目的としています。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性の向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目指しています。
A. 本事業の申請は、電子申請システムのみで受け付けられます。申請者は、中小機構が提供する電子申請システム操作マニュアルに従い、自ら入力作業を行う必要があります。入力情報の内容を十分に理解・確認した上で、申請者自身が申請を行うことが求められており、補助金の電子申請システムでは代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供されていません。申請者自身による申請と認められない場合には、不採択となります。
A.
補助対象となるためには、主に以下の基本要件を満たす必要があります。 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上の増加 1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上の増加 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 従業員数21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等 ただし、最低賃金引上げ特例適用事業者の場合は、1、2、4のみが基本要件となります。これらの基本要件が未達の場合、補助金の返還義務が発生する可能性があります。
A. 補助対象となる主な経費は、機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費です。ただし、補助対象経費は交付決定日以降に発注し、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます。また、機械装置・システム構築費については、単価50万円(税抜)以上の設備投資が必須です。汎用性が高く、目的外使用になり得るものや中古品の購入費、自社の人件費などは補助対象外となります。補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込み)の3分の2以上である必要があり、支払いは原則として銀行振込で行う必要があります。
A. 審査では、補助対象事業としての適格性、技術面(省力化指数、投資回収期間、付加価値額、オーダーメイド設備の導入など)、計画面(事業遂行体制、実現可能性、収益性、賃上げ目標の妥当性、会社全体のシナジー効果など)、政策面(地域経済への貢献など)が総合的に評価されます。一定の補助額を超える申請については、書面審査に加えてオンラインでの口頭審査が実施される場合があります。口頭審査では、事業計画の内容や意思決定の背景などが確認され、申請者自身(法人代表者等)が対応する必要があります。
A. 補助金の交付を受けた場合、説明会への参加、取得財産(特に単価50万円以上の機械等)の適切な管理と処分制限、消費税等仕入控除税額の報告、補助金等適正化法等の遵守、事業実績報告と効果報告の提出、証拠書類の保管、会計検査への協力などが義務付けられます。特に、事業終了後も一定期間にわたり、省力化効果や賃上げ状況などの効果報告を行う必要があります。目標が未達成の場合には、補助金の返還を求められることがあります。
A. 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)は、事前に登録された省力化製品の中から選択して導入する事業者を支援するものです。一方、(一般型)は、中小企業等が自社の課題に合わせてオーダーメイドの設備やシステムを導入する、または汎用的な設備を導入するものの、周辺機器や構成、機能などを事業者の環境に合わせて変更・組み合わせることで高い省力化効果や付加価値を生み出す投資を支援します。(一般型)でカタログ注文型に登録されているカテゴリに該当する製品を導入する場合でも、単に製品カタログに掲載されている製品をそのまま導入するのではなく、事業者の導入環境に応じたカスタマイズや、複数の汎用設備との組み合わせによる高い省力化効果が示されていれば、審査において考慮されることがあります。
「補助対象となるのはどんな事業者?申請前に確認すべき基本要件と対象外となるケースを詳しく解説」

本補助金の対象者は、一定の要件を満たす国内の中小企業者および一部の非営利法人です。 ただし、要件を満たさない場合や申請資格がないケースも存在するため、事前の確認が不可欠です。
- 対象者:国内に本社および補助事業を実施する拠点を有する中小企業者、 NPO法人、社会福祉法人など
- 資本金または従業員数に基づく中小企業の定義に該当していること
- 事業実施場所が日本国内にあること
- 基本要件:
- 3~5年の事業計画を策定し、年平均成長率4.0%以上の労働生産性向上を見込む
- 事業場内最低賃金の引き上げや、給与支給総額や一人当たり給与支給総額の増加目標を設定
- 従業員21名以上の場合は、一般事業主行動計画の公表が必要
- 対象外となるケース:
- みなし大企業(大企業が実質的に経営に参画している中小企業 など)
- 補助金の重複支援(国の他の助成制度と同一内容の事業)
- 汎用設備を単体で導入するだけ(省力化投資や付加価値向上の効果が不明確)
- 経営体制が不十分で事業継続が困難と判断される場合
- 主体的な申請: 本補助事業は、あくまで申請者自身が主体的に計画・実施を行い、補助金を活用することが 前提です。外部コンサル等を活用しても、最終責任は申請者にあります。
「いくら補助される?補助上限額と補助率、大幅賃上げ特例を活用するための条件と注意点」

本補助金には、従業員規模や賃上げ目標に応じて補助率や補助上限額が異なる仕組みがあります。 さらに、大幅な賃上げに取り組む事業者には特例措置が設けられる場合があります。
- 補助上限額と補助率
- 従業員5名以下:補助上限 200万円(賃上げ特例:+100万円)
- 従業員6~20名:補助上限 500万円(賃上げ特例:+250万円)
- 従業員21名以上:補助上限 1,000万円(賃上げ特例:+500万円)
- 補助率は通常1/2(オーダーメイド設備や赤字事業者などで要件を満たす場合 2/3)
- 大幅賃上げ特例:
- 給与支給総額(または一人あたり給与支給総額)の年平均成長率が 6.0%以上などの要件を満たす場合に補助上限額の引き上げが可能
- 特例を適用するには、事業計画書で具体的な賃上げ計画を明示する必要あり
- 補助対象となる経費:
- 機械装置・システム構築費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費など
- 技術導入費や専門家経費も対象。ただし経費ごとの上限や相見積もり義務に注意
- 補助対象外の経費:
- 建物取得費や汎用的な事務機器、中古品購入費、自社の人件費 など
- 交付決定前に契約・購入した経費
- 趣旨に合わない経費(飲食費・接待費など)
「中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請方法と審査のポイント:電子申請の流れ、事業計画書の書き方、加点項目」

申請は原則として「電子申請システム」を通じて行います。GビズIDプライムの取得や 事前登録が必要なため、余裕を持って準備を進めましょう。
- 電子申請のステップ:
- GビズIDプライムの取得(すでに取得済みの場合は不要)
- 申請マイページの開設・ログイン
- 必要情報の入力、提出書類(事業計画書・見積書・会社情報等)のアップロード
- 申請完了後、審査結果の通知を待つ
- 事業計画書の書き方:
- 省力化効果やDX導入効果を定量的に示す(生産量、工数削減率、付加価値額など)
- 投資回収期間を試算し、想定収益を具体的に記載
- 会社全体のビジネス戦略との整合性を示し、経営計画とリンクさせる
- 賃上げ目標の根拠や達成のロードマップを明確化
- 審査の着眼点:
- 補助対象事業としての適格性(人手不足解消・生産性向上に寄与するか)
- 技術面(省力化指数、オーダーメイド設備の独自性、付加価値額の向上)
- 事業計画の実現性と妥当性(資金計画や投資回収シミュレーション)
- 賃上げや地域経済への波及効果
- 加点項目:
- 事業承継・M&Aなどを伴う場合
- 事業継続力強化計画を策定済み
- 賃上げ加点(大幅賃上げ特例に該当など)
- えるぼし・くるみん認定、成長加速マッチングサービス登録 など
- 外部支援者の記載義務: コンサルタント等による申請書作成支援を受けた場合、その支援者名や業務内容を申請書に 記載する必要があるので注意してください。
過去の採択事例から学ぶ傾向について

中小企業省力化投資補助金(一般型)の採択傾向を把握し、採択されるための対策を講じることは、申請を成功させる上で非常に重要です。以下に、公募要領で示されている審査項目と、採択事例に共通すると考えられる傾向、そして具体的な対策を示します。
主要な審査項目と採択傾向
- 事業の適格性:
- 補助事業の目的(人手不足の解消、生産性向上、売上拡大、賃上げ)に合致しているか。
- 補助対象外の事業に該当していないか。
- 採択傾向: 補助金の趣旨を正しく理解し、明確な課題意識と目標を示した事業計画が重視される。
- 革新性・優位性:
- 独自の技術やアイデアがあるか、または省力化指数・投資回収期間・付加価値額などが優位か。
- オーダーメイド設備をはじめとするデジタル技術の活用などを評価。
- 採択傾向: 単なる設備の買い替えではなく、組み合わせやDX活用による「高い省力化効果」を示す計画が有利。短い投資回収期間や高い付加価値創出が鍵。
- 実現可能性:
- 事業を実行できる社内外の体制、人材、専門知見、財務状況があるか。
- スケジュールが無理なく、金融機関などの資金調達見込みがあるか。
- 採択傾向: 具体的な実施体制や明確なスケジュール・資金計画を示すほど信頼度が高い。
- 計画面(収益性・生産性・賃金向上):
- 労働生産性・給与支給総額・最低賃金引き上げ目標などが設定されているか。
- 根拠が明確で、実現性が高いか。
- 採択傾向: 具体的な数値目標を設定し、その算出根拠を明確に説明できる事業計画が採択されやすい。
- 政策面:
- 地域経済の活性化や、国の経済政策上の優先分野へ貢献しているか。
- 雇用創出、地域連携など、広い視野での効果が見込まれるか。
- 採択傾向: 地域の特性を活かし、雇用や地域経済に波及効果をもたらす取組が評価されやすい。
- 大幅賃上げ特例:
- 大幅賃上げ(給与支給総額の年平均成長率+6%以上など)に取り組む計画が具体的か。
- 一時的ではなく継続的に従業員へ還元できる見込みがあるか。
- 採択傾向: 将来にわたり賃上げを持続できる仕組みが整っており、人材育成や体制強化を視野に入れた計画が評価されやすい。
採択されるための対策
- 明確な事業目的と課題設定:
- 自社の現状を分析し、人手不足の要因や生産性向上が必要な背景を具体的に示す。
- 補助金の趣旨(省力化投資による賃上げなど)との整合性を明確に。
- 具体的な省力化投資計画:
- 導入予定のIoT・ロボット・DX技術について、型番や導入スケジュールを含めて具体的に記述。
- 汎用設備を導入する場合でも、高い省人化効果や組み合わせの工夫をアピール。
- 定量的・定性的な効果説明:
- どの工程がどの程度省力化されるか、どのくらい人件費・工数が削減されるかを数値で示す。
- 人的ミス削減や労働環境改善などの定性的なメリットも補足。
- 実現可能性の高い事業計画:
- 実施体制(誰が何を担当するのか)、財務状況(資金繰り)などを明確に説明。
- 金融機関等からの資金調達を予定している場合は、確認書などで裏付け。
- 詳細なスケジュールを作成し、交付決定日から事業完了日までの流れを具体化。
- 収益性・生産性・賃金向上への貢献:
- 労働生産性や給与支給総額の算出根拠を緻密に示す。
- 事業場内最低賃金の引き上げ、従業員一人当たり給与支給総額の増加などを具体的に計画化。
- 省力化によって創出された労働余力を、どのように高付加価値業務へ転換するかを示す。
- 政策への貢献のアピール:
- 地域経済や雇用への波及効果、産業クラスター形成など、広い視点での効果をアピール。
- 国の省力化投資促進政策にどう寄与するかを明示する。
- 加点項目の積極的な活用:
- 事業承継・M&A、事業継続力強化計画、成長加速マッチングサービスへの登録、賃上げ加点など
- えるぼし・くるみん認定などがある場合は書類を添付し、ポイントを稼ぐ。
- 正確で分かりやすい申請書類の作成:
- 公募要領を熟読し、要求される項目をもれなく記載。
- 図表や写真を活用して視覚的に伝える。
- 虚偽や誇張は厳禁。不正が発覚した場合、返還命令や公表など厳しい措置がとられる。
- 電子申請システムの理解:
- 事前にGビズIDプライムを取得し、申請マイページの操作手順を確認。
- 提出書類はPDFなど所定の形式でアップロード。
- 口頭審査への備え:
- 申請内容を十分に把握し、質問に的確に答えられるよう準備する。
- コンサルタントの同席は不可。申請者自身が責任を持って対応。
これらの対策を十分に講じ、審査項目に合致した事業計画を立案・申請することで、中小企業省力化投資補助金(一般型)の採択率を大幅に高められるでしょう。
【まとめ】令和7年度中小企業省力化投資補助事業(一般型)を最大限に活用しよう

中小企業省力化投資補助事業(一般型)は、人手不足に悩む中小企業や小規模事業者の売上拡大、生産性向上を後押しするために、IoT・ロボットなどの人手不足解消に効果がある設備を導入する際の費用の一部を補助し、省力化投資を促進することを目的としています。人力の部分をロボットに置き換えたりと、人材不足が課題な現代社会でも生き残れるように対策をしましょう。
申請を検討中の方は、早めに公募要領をチェックし、連携体制や計画をしっかり固めましょう。複雑な手続きに関しては、支援機関やコーディネーターに相談しながら進めるとスムーズです。ぜひ、本補助金を活用して、社会課題解決とビジネスチャンス拡大を同時に目指してください。
弊所では、各種補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、 事業計画書などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご利用いただけます。
また、弊所では補助金申請~採択までだけではなく、採択後の実績報告等もしっかりとサポートさせて頂きます。
2025年度のその他補助金についてはこちらの記事でご紹介しております。
「2025年度補助金情報」
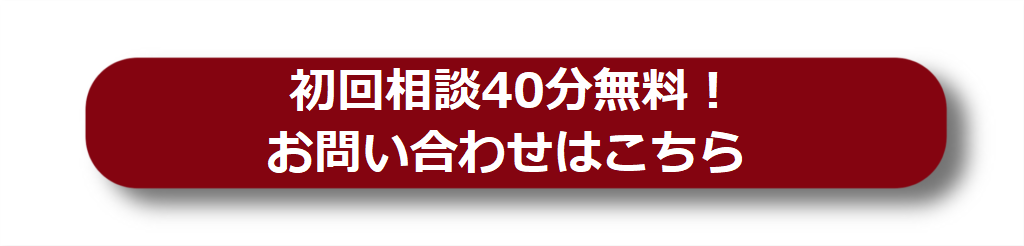
関連記事はこちら
[post_grid id=”2369″]
| 事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
|---|---|
| 英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
| 代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
| 所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
| 取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
| TEL | 075-241-3150 |
| 営業時間 | 9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】 ※メールでの相談は年中無休で受付けております。 |
