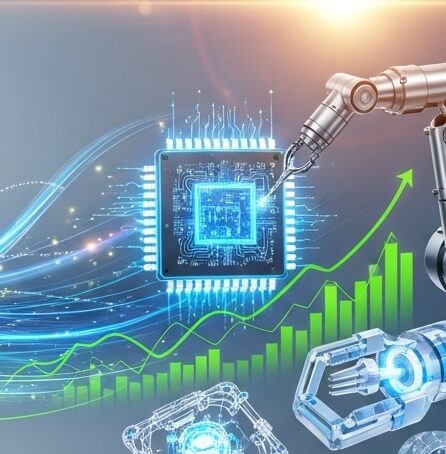【2025】「産学公の森」推進事業補助金
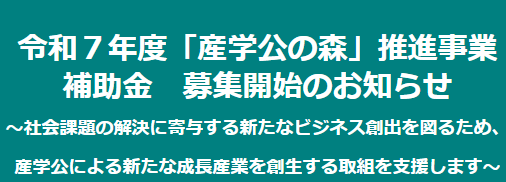

2025年度「産学公の森」推進事業補助金について解説致します。
本記事の内容
・ 【令和7年度】京都府「産学公の森」推進事業補助金:社会課題解決を目指す産学公連携を支援
・ 京都の中小企業・大学等研究機関必見!「産学公の森」補助金で新たなビジネス創出を
・ 脱炭素、スマートシティ、ヘルスケア…「産学公の森」補助金が支援する社会課題解決の具体例
・ 「産学公の森」補助金 申請のポイント:対象要件、補助率、申請手続きを徹底解説
・ 過去の採択事例から学ぶ傾向について
・ まとめ
【令和7年度】京都府「産学公の森」推進事業補助金:社会課題解決を目指す産学公連携を支援
概要と目的
令和7年度に実施される京都府の「産学公の森」推進事業補助金は、大学や研究機関、中小企業、行政機関などが連携し、社会課題解決を目指す取り組みに対して資金面で支援を行う制度です。
脱炭素やスマートシティ、ヘルスケアといった領域を含む、多様な課題の解決に向け、産学公連携による共同研究・開発・実証を促進することが目的です。
背景
- 人口減少や高齢化、環境問題など、複雑化する社会課題を単独で解決するのは難しい
- 大学等の研究機関の先端技術と、企業のビジネスノウハウ、行政の調整力を組み合わせてイノベーションを創出
- 研究開発から実証・事業化まで総合支援し、京都の産業力・競争力の向上を図る
期待される成果
- 共同研究開発や実証を通じた新技術・新サービスの確立
- 産学公連携によるイノベーション拠点形成と地域経済の活性化
- 国内外への市場展開やビジネスモデルの拡張
A. 本補助金は、地球温暖化や食糧問題といった様々な社会課題の解決に貢献するため、企業や大学等の研究機関、そして公的機関が連携し、それぞれの強みを活かして新たなビジネスや成長産業を創出する取り組みを支援することを目的としています。単独の企業では解決が難しい社会課題に対し、オープンイノベーションによる社会課題解決型ビジネスの創出を促進します。特に、京都府が推進する「産業創造リーディングゾーン」に関連する取り組みや、グローバル展開を目指す取り組みなどが重視されています。
A. 補助金の対象となるのは、京都府内に事業活動の拠点を有する中小企業者を代表企業とし、構成企業または大学等研究機関を含む2者以上で構成される「産産連携グループ」または「産学連携グループ」です。代表企業と構成企業・機関は、共同事業契約を締結し、相互に協力して事業を実施する必要があります。大学等研究機関は京都府外に所在地があっても構いません。ただし、グループ間の受発注に係る経費は補助対象外です。また、一定要件を満たす「スタートアップ企業」が構成企業として参加する場合は、京都府内に拠点がなくてもグループ構成要件を満たすとされます。
A.
本補助金では、社会課題の解決に資する幅広い分野の新たなビジネス創出を支援しており、具体的な例として以下の分野が挙げられています。 ビッグデータ解析等の先端技術を活用した子育て環境の構築 脱炭素社会の実現に向け「自然」の機能を活かす新産業の振興 メタバース、デジタルツインなどのテクノロジーを組み合わせたスマートシティの構築 フードテック、スマートアグリの技術を活用した第一次産業の課題解決に資する取組 「京の健康」で示された健康寿命延伸のためのヘルスケア産業の振興 これらはあくまで例示であり、上記以外の社会課題解決に資する多様な取り組みが期待されています。
A. 本補助金には、事業の段階に応じて「アーリーステージコース(グループ形成)」、「事業化促進コース(試作・開発、テストマーケティング)」、「本格的事業展開コース(応用研究等、設備投資、それらと連動した販路開拓)」の3つのコースがあります。 アーリーステージコース: 1グループあたり120万円以内、補助率は対象経費の1/2以内です(勉強会・研究会の実施は20万円以内)。 事業化促進コース: 1グループあたり100万円以上2,000万円以下、補助率は対象経費の1/2以内です。 本格的事業展開コース: 1グループあたり2,000万円超5,000万円以下(1企業あたり3,000万円以内。ただし、産学連携グループで大学等研究機関との受託(共同)研究費がある場合は2,000万円まで加算可能)、補助率は対象経費の1/2以内、土地造成費、建物建設費、本格的な生産・販売目的の設備については15%以内です。
A. 申請者は、所定の申請書類を作成し、受付期間内に公益財団法人京都産業21に郵送または持参により提出します。その後、Ⅰアーリーステージコースは書面評価、Ⅱ・Ⅲコースは書面評価とプレゼンテーション評価を経て、採択されたグループには交付決定通知書が送付されます。交付決定後、実績報告書の提出、額の確定を経て、補助金が交付されます。補助事業完了後も、一定期間(Ⅰコースは1年間、Ⅱ・Ⅲコースは5年間)、事業化の状況等について報告を行う必要があります。
A. 補助対象経費は、補助事業に直接関係する経費であり、具体的には以下のものが挙げられます。 旅費(構成メンバーの事業活動に必要な公共交通機関の利用に限る) 直接人件費(補助事業に直接関与する構成メンバーの人件費。上限あり) 材料費・消耗品費 機械装置及び設備・備品等の購入費、リース料、割賦料、製作・改造費 土地・建物の賃借料(対象期間分のみ) 外注・委託費(補助事業の核となる要素の全てを委託することは不可) 大学等研究機関との受託(共同)研究費(間接経費を含む。対象期間分のみ) その他直接経費(会議費、広告料、パンフレット等作成費、知的財産権の出願等に要する経費、展示会出展費用など) ただし、事前着手期間中の直接人件費や、汎用性の高い事務用品、既存の建物・設備の解体費、公租公課などは対象外となります。
A. 申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。 グループ構成要件を満たしていること(代表企業は京都府内の中小企業者であることなど)。 申請書類に不備がないこと。 提出された書類の内容(個人情報を含む)は、京都府にも提供されること。 他の補助金と重複して同じ経費を申請することはできません。 申請者(代表企業・構成企業)が反社会的勢力に該当しないこと。 過去に国や地方公共団体等の補助金で不正経理・不正受給等がないこと、法人税等の滞納がないこと。 補助事業期間中に拠点を府外に移転する計画がないこと。 「パートナーシップ構築宣言」への協力が推奨されています。
京都の中小企業・大学等研究機関必見!「産学公の森」補助金で新たなビジネス創出を

対象者:中小企業・大学等研究機関
本補助金は、中小企業や大学・公的研究機関が主体的に参画するプロジェクトが対象になります。単独企業での取り組みではなく、学術機関や行政との連携が必須となる点が大きな特徴です。
メリット
- 資金的負担の軽減:開発・実証にかかるコストを補助金で補える
- 産学公ネットワークの拡大:大学の研究成果を企業が製品化し、行政が地域での導入を支援
- 社会課題解決型ビジネス:社会性の高いテーマで新規事業のチャンスを獲得
具体的なビジネス創出事例
- 大学発ベンチャーとのコラボ:大学研究成果を製品化し、行政支援を受けて早期市場化
- 先端技術の社会実装:AI、IoT、バイオ技術などを地域課題と結びつけ、新規サービス開発
脱炭素、スマートシティ、ヘルスケア…「産学公の森」補助金が支援する社会課題解決の具体例

脱炭素、スマートシティ、ヘルスケア…「産学公の森」補助金が支援する社会課題解決の具体例
脱炭素領域
再生可能エネルギーや省エネルギー技術の共同開発・実証など、企業と大学が一体となり次世代の環境ソリューションを育成します。
スマートシティ領域
交通・インフラ・街づくりをDX化し、住民の生活を向上させる取り組み。AIによる交通最適化、スマート街路灯、災害情報システムなどを産学公連携で検証します。
ヘルスケア領域
遠隔医療システムや介護ロボット、認知症予防プログラムなど、高齢化社会に対応する新技術の開発・実証に補助金を活用できます。
「産学公の森」補助金の効果
- 大規模・複雑な社会課題に対し、大学の研究力×企業の実装力×行政の調整力で解決策を加速
- 実証経費を補助することで、課題解決のスピードと成功率を高める
「産学公の森」補助金 申請のポイント:対象要件、補助率、申請手続きを徹底解説

対象要件
- 京都府内に拠点を有する中小企業または大学・公的研究機関が参画している
- 産学公連携(企業+学術機関+行政)による共同プロジェクト
- 脱炭素、スマートシティ、ヘルスケアなど、社会課題解決を目的とした研究開発・実証・事業化
補助率と補助上限額
補助率は、原則1/2~2/3以内が想定され、上限額は数百万円~数千万円程度(詳細は公募要領を確認)。
申請手続きの流れ
- 公募要領の確認:京都府や支援機関のサイトで公募情報を入手
- 共同体制の構築:企業、大学、行政などの連携主体を決定し、プロジェクト計画を策定
- 書類作成:研究・開発内容、予算計画、期待効果、スケジュールなどを詳細に記載
- 提出・審査:指定様式で申請し、審査やプレゼンテーションを経て採択
- 採択・交付決定:交付決定後に事業開始
- 実績報告・検査:事業完了後、支出証憑や成果報告を提出し、補助金が交付
注意点・成功のコツ
- 産学公の連携実績や具体的な協力関係を明確に示す
- 社会課題との関連性や解決策の優位性を定量的に示す
- 計画書の完成度(スケジュール、予算内訳、リスク管理等)が審査で重要
過去の採択事例から学ぶ傾向について

1. 令和5年度(R5)の採択結果と分析
(1) 採択概要
- Ⅰ アーリーステージコース:11件
・ メタバース/Web3.0技術と京都文化の融合
・ アップサイクルやAI/AR活用、健康食品開発など幅広いテーマ - Ⅱ 事業化促進コース:14件
・ CO2分離回収、バイオ診断薬、伝統産業×クリエイターのコラボなど
・ 医療・ヘルスケアの事業化や大豆ミートの活用など多様 - Ⅲ 本格的事業展開コース:6件
・ ペロブスカイト太陽電池、バイオマス木材、iPS細胞の再生医療
・ 環境・エネルギー分野を中心に高度技術の実用化を目指す案件が多い
(2) 傾向・特徴
- AI・バイオ・再生医療、環境エネルギー領域が特に注目
- メタバース/NFT、ARなどのデジタル技術との掛け合わせが増加
- 伝統産業や食品、農産物のアップサイクルによるSDGs・地域課題解決を重視
(3) 令和5年度の成功要因・対策
- 多分野を横断した斬新なアイデアが採択されやすい
- 大学・研究機関との連携を通じて学術的エビデンスや技術強度を高める
- 伝統×先端技術や海外市場開拓など、掛け合わせの新規性が鍵
2. 令和6年度(R6)の採択結果と分析
(1) 採択概要
- Ⅰ アーリーステージコース
応募15件 → 交付決定14件(約93%)
・ プラズモニック印鑑、アルツハイマー病ワクチン、AI創薬、耳コピメソッドなど - Ⅱ 事業化促進コース
応募28件 → 交付決定15件(約54%)
・ 廃プラのケミカルリサイクル、EV急速充電器、森林解析用ドローンなど - Ⅲ 本格的事業展開コース
応募7件 → 交付決定7件(100%)
・ iPS細胞由来膝関節、遺伝子改変ブタ、歯科麻酔用マイクロニードルなど
・ 大学の研究成果を量産化・商用化するプロジェクトが目立つ
(2) 傾向・特徴
- AI・DX技術のさらなる高度化(AI創薬、脳活動観測、物流DX等)
- 環境リサイクル・EV・CO2削減など、脱炭素社会向けプロジェクト増加
- 医療・バイオでの臨床応用や量産化を狙う案件が顕著
(3) 令和6年度の成功要因・対策
- 実証・量産化の具体性+大学との連携実績が高評価に繋がる
- CO2削減やバイオ技術など社会的ニーズが強いテーマほど採択率高
- 研究成果の事業化ストーリーを明確に示し、リスク管理&収益計画を練る
3. 2年分(R5・R6)における全体的な共通傾向
- AI・DX、バイオ・再生医療、環境・エネルギーの3大領域が継続的に高評価
- 伝統産業×先端技術や地域資源活用など、京都の強みを活かした新規性
- SDGs/カーボンニュートラルを意識したCO2排出削減や廃棄物リサイクルが多い
- 産学公連携による大規模プロジェクトが増加し、設備投資や海外展開まで視野
4. 今後の申請に向けた対策・ポイント
- 高度技術×社会課題の掛け合わせ:AI・バイオ・環境技術を使い、地域課題やSDGsに直結するプロジェクトが狙い目
- 大学・研究機関との連携強化:特許や研究成果をビジネスに落とし込む具体的計画が評価されやすい
- 実用化・拡大戦略の明確化:量産体制や販路、収益モデルを示し、リスク管理を明記
- 社会・環境インパクトのアピール:CO2削減量や地域活性化など、定量的指標を示す
- 専門家・コーディネーターの活用:書類作成や連携体制構築をスムーズに行うため、支援機関をフル活用
まとめ
令和5年度・令和6年度の「産学公の森」推進事業を見ると、AIやバイオ、脱炭素などの 先端分野での研究開発・実用化が特に多く採択されています。京都らしい伝統技術との 組み合わせやSDGsを意識したアップサイクルなど、社会課題解決型のビジネスも 引き続き高い評価を得ています。
今後の申請を検討する事業者の方は、大学・研究機関との連携を軸に学術的根拠を しっかり示しながら、事業計画の実現性や社会的インパクトを 具体的かつ定量的に示すことが成功へのカギです。事業がスケールアップするほど採択可能性が 高まる傾向があるので、ぜひ戦略的な申請を目指してください。
【まとめ】令和7年度「産学公の森」推進事業補助金を最大限に活用しよう

京都府が実施する「産学公の森」補助金は、社会課題解決を目的とした産学公連携を支援する大きなチャンスです。脱炭素やスマートシティ、ヘルスケアなどの領域で、中小企業や大学研究機関が連携し、新たなイノベーションを創出できます。
- 補助率最大2/3以内(コース・要件次第)
- 研究・実証経費をサポートしてリスクを軽減
- 産学公が一体となることで、高度な課題解決とビジネス化が可能
申請を検討中の方は、早めに公募要領をチェックし、連携体制や計画をしっかり固めましょう。複雑な手続きに関しては、支援機関やコーディネーターに相談しながら進めるとスムーズです。ぜひ、本補助金を活用して、社会課題解決とビジネスチャンス拡大を同時に目指してください。
弊所では、各種補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、 事業計画書などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご利用いただけます。
また、弊所では補助金申請~採択までだけではなく、採択後の実績報告等もしっかりとサポートさせて頂きます。
2025年度のその他補助金についてはこちらの記事でご紹介しております。
「2025年度補助金情報」
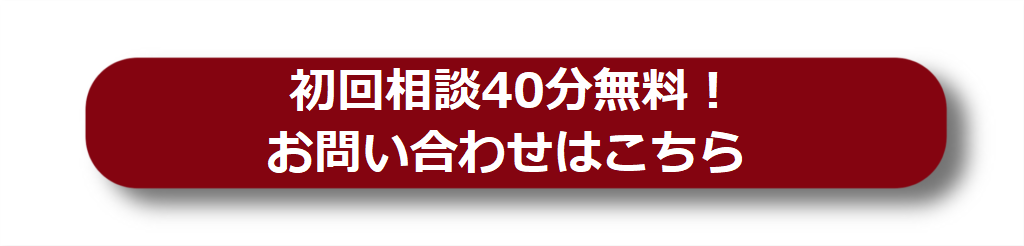
関連記事はこちら
| 事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
|---|---|
| 英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
| 代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
| 所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
| 取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
| TEL | 075-241-3150 |
| 営業時間 | 9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】 ※メールでの相談は年中無休で受付けております。 |